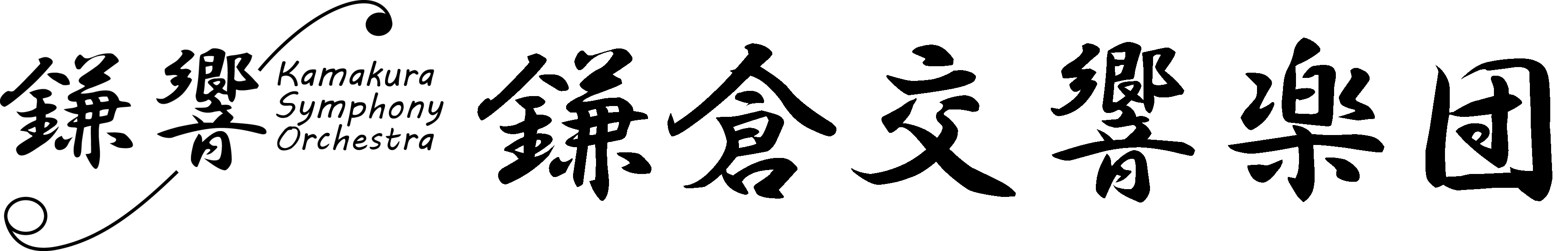第125回定期 𠮷﨑 理乃(指揮)鈴木隆太郎(Pf)インタビュー
来たる6月21日(土)開催の第125回定期演奏会の指揮者𠮷﨑理乃、シューマンのピアノ協奏曲でソロをつとめる鈴木隆太郎に演奏会に向けてインタビューしました。
𠮷﨑理乃のプロフィールはこちら
鈴木隆太郎のプロフィールはこちら
(聞き手:当団コンサートマスター 五味 俊哉)

ともに鎌倉の学校に学び楽壇に巣立つ
Q:お二人とも平成生まれで、鎌倉とご縁が深いという共通点があります。地元鎌倉から音楽家を目指すことになった経緯や、今回地元のアマチュアオーケストラである鎌響と共演する思いを教えてください。
A:(𠮷﨑)
まだ小学生のころ、指揮者マリス・ヤンソンスがウィーンフィルのニューイヤーコンサートで指揮をするのをテレビ中継で観て、その指揮に感銘を受け、ヤンソンスのような人になりたいと思いました。当時人気を博していた「のだめカンタービレ」にも大いに影響され、いつか指揮者になりたいと思うようになりました。藝大に進学する、という目標を固めつつ、中高6年間北鎌倉女子学園に通っていました。
地元で活躍する鎌響は当然知っていましたが、ご縁ができたのは東京藝大指揮科での私の先輩であった指揮者が鎌響で指揮をすることになったご紹介いただいたことがきっかけでした。
中高校生時代に毎日過ごしていた鎌倉で、地元鎌響の指揮をすることになったのはほかの仕事とは違った特別感があります。
A:(鈴木)
小さいころから漠然と、ピアニストになりたいと思い続けていました。その中で、当時栄光学園高等学校に通っていましたが、ピアニストになりたい、という自分の志に対して、先生方が背中を押してくださった結果、日本の大学ではなく、パリ国立高等音楽院に留学することになったのです。
その後、その難しさも含めて職業としてピアニストになりたいと確信を持てたのは、留学後2年が経ってからです。
いまはパリを拠点に海外を活動の中心においているのですが、海外では当然様々なバックグラウンドの演奏者と触れ合うことになります。そんな多くの音楽家たちとの出会いの中でも日本人同士、更に鎌倉出身同士というということで、𠮷﨑さんにはたいへん親近感が沸きます。自分にとってやはり鎌倉は特別な感覚のある街で、歴史のある鎌響も以前から知っていましたし、今回鎌響とご一緒させていただけるのはとても嬉しいことです。
音楽を仕事にすることの緊張感と対策
Q:𠮷﨑先生は、前回鎌響で振っていただいてから、東京国際指揮者コンクール2024にて第三位、更にN響ともこの先共演予定とのことで、大きく飛躍されていますね。
最近の環境変化やご自分の意識について教えてください。

A:(𠮷﨑)
芸大の指揮科の学生は毎年1回、1月にある学年末試験で芸大フィル(大学のプロオケ)を指揮することができます。そこで何度か指揮した経験はありましたが、昨年の8月に初めてプロオケを振らせていただく仕事をいただきました。自分のステップアップのためコンクールにも出ることにしました。それぞれプレッシャーの大きな緊張する場でしたが、プロのオケは奏者一人一人から伝わってくるパワー、管楽器の音圧もすごいと感じました。プロ奏者たちの本番へのコンディションの持って行き方、集中力やサウンドを集めていくエネルギーを指揮台で浴びることができたことで自分も成長することができたように感じました。
プロオケとの共演では仲間というよりは、オケを引っ張っていかないといけない指揮者の使命があるので、リハーサルではプレッシャーを感じますが、その緊張感も含めとてもやりがいがあります。
一方鎌響のようなアマオケとのお仕事では、オーケストラのメンバーと自分が双方向でコミュニケーションをとりながらいっしょに演奏を作っていこう、という仲間意識を感じることができ、それが楽しいです。
Q:鈴木先生は、海外で1年の半分以上を過ごされ、さまざまな海外の地で公演をされていると伺っています。そういう演奏活動で感じる緊張やそれへの対策について教えてください。

A:(鈴木)
海外での仕事では、演奏する場がどういう環境なのか、行ってみないとわからない、ということでとても緊張感があります。
以前は、本番で自分のベストの状態にしていくために、いわゆる「ルーティン」(験担ぎ的なコンディション作り)がありました。日本では、例えば本番前に必ずこの水を飲もう、と決めたら近くのコンビニなどで確実に手に入りますが、海外では飲料水すら手に入りにくい劣悪な環境の場所も未だにあるのです。
そのような場で演奏することになった場合に、ルーティンができなかったことで演奏がうまくいかない、というような言い訳になることを排除するため、あえて本番前のルーティンは一切つくらない、ということを自分で決めました。
さまざまな環境下で、本番へ自分のベストを持って行く、という準備の仕方はアスリートぽいところもありますね。緊張しそうな本番から逆算して、2~3日単位で心身共にコンディションの整えて仕上げていくことにしています。
名曲の演奏にあたっては誠実に楽譜に向かう
Q:今回はドイツロマン派の王道を行くようなプログラムでどれも鎌響でも何度も演奏してきたものばかりの有名曲ですが、音楽作りの上でのこだわりなど有りましたら教えてください。
A:(𠮷﨑)
自分はいままでは、他のオーケストラでもここまでのドイツロマン派王道のプログラムを振ったことはなく、私としては新鮮なアプローチです。作曲家それぞれのレパートリーの中でも特別な曲であり、すばらしいプログラムだと思います。
定番の名曲だと1~2回のリハーサルだけで本番に臨むことが多いプロオケとは違い、鎌響では数か月の時間をかけて練習して仕上げていくわけですが、そのプロセスが自分にとっても勉強になり、練習の度に、もっとこうしないといけないな、とか自分でも考えなおしたりすることが多くあります。そうしていると、やはり時間をかけて醸成していく価値のある名曲だ、と感じますね。
エグモントもブラームスの3番も名曲で、過去の巨匠指揮者の演奏が耳になじんでいるお客様も多いと思います。演奏速度などは過去の大指揮者の演奏と違うと思われるかもしれませんが、私は作曲家が楽譜に書いたことを誠実に再現し、お届けしたいと思っています。

A:(鈴木)
グリーグとシューマンのピアノ協奏曲(ともにイ短調)は、良くカップリングして録音されます。私自身は、グリーグは何度か演奏経験がありますが、今回のシューマンはオケと共演するのは実は初めてなので、とても楽しみにしています。僕がイタリアで学び、シューマンがお得意だったヴィルサラーゼ先生のアドバイスを取り入れさせていただいたりしながら表現のしかたを検討してリハーサルに臨んでいます。
𠮷﨑さんと同じ方向性の発言ですが、音楽で一番大切なのは楽譜に記載してあることだと思います。楽譜に誠実でありながら、自分が感じたことをそのまま表現したいと思います。
地元鎌倉への思いを込めて
Q:最後に、鎌響ファンのお客さまに向けてメッセージをお願いしま
A:(𠮷﨑)
鎌響は、幅広い年齢層のメンバーで構成されていることが大きな特長だと思います。
王道のプログラムを、人生経験豊富な鎌響の皆さんと一緒に演奏できることを自分自身が楽しみにしています。
本番まであと一か月、より演奏に磨きを掛けていきたいと思いますので、皆さまもお楽しみにしてください。
A:(鈴木)
今日の初リハーサルで初めていっしょに演奏をしたのですが、やはり鎌響は自分の故郷のオケであり、鎌響の支えのおかげで自分のやりたい音楽が表現できるという喜びを感じることができました。
昔から生まれ育った鎌倉で、歴史のある鎌響と、初めて共演できることに大きな意味を感じ、楽しみにしています。特に鎌倉の皆様には是非聴きに来ていただきたいと思っています。
(2025年5月18日 YMCA東山荘)